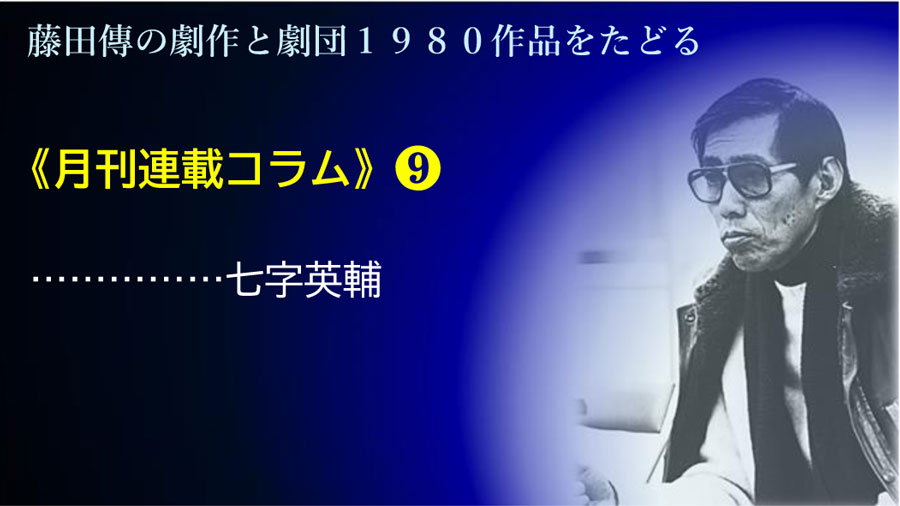| かつて私は、俳優座版『とりあえずの死』を称して「新しい『記録演劇』の誕生」と書いたことがある(俳優座『南回帰線にジャポネースの歌は弾ね』プログラム/1995年)。「記録演劇」とはフィクションを交えずに、出来る限り過去の事件や出来事を忠実に再現した演劇を謂うのだが(私の頭の中には、原爆投下直後の広島博愛病院の医師たちの活動をリアルタイムで描き出す大橋喜一作『ゼロの記録』(68年/劇団民藝)や映画『オッペンハイマー』でも描かれた「オッペンハイマー裁判」の記録たるキップハルト作『オッペンハイマー事件ー水爆・国家・人間』(65年/劇団青俳)、さらには燐光群による、墜落事故を起こす直前の航空機内のコックピットを描く『CVR 』(02年)などが直ぐに思い浮かぶ)、『とりあえずの死』は、言うまでもなくそれらとは異なる。
それではすべてが作者の主観に基づくフィクションかといえば、それも違う。藤田は、当時はまだ現存したハルビンの「中国外僑養老院」に、演出の西木、女優の美苗らを伴って取材旅行を敢行していて、そこで会った4人の日本人残留婦人たちを、4人に年齢の近いベテランに演じさせ、「養老院」の臨場感を醸し出した。4人とは、村瀬演じる桜井芳の他、植田貞美(中村たつ)、亀石光子(岩崎加根子)、大悟法瀧江(阿部百合子)の面々。貞美は終戦前に夫が応召、乳飲み子を抱えて開拓団から自力で関東軍司令部のあった新京(現・奉天、満州国の首都)に向かう。光子は内地で看護婦をしていたが、勤労奉仕団から派遣、新婚7カ月での夫婦での移民。瀧江は先に入植していた夫と現地結婚、開拓花嫁であった。認知症を患っていて、徘徊癖のある芳のみ来歴が不明だが、大連での社交ダンスの場面が出てくることから彼女は開拓民ではなく、満州駐在の夫に同行した家庭人か職業婦人だったのだろう。しかし、引き揚げの際の苦労は他の3人と変わらない。
これらのことは彼女たちの夜を徹しての問わず語りの語り合いから知られることだが、問題は、それぞれに「分身」が憑くことだ。それぞれの若き日の自分たちの証言者として彼女らの前に現れる昔の姿のままの「分身」。宮本研『花いちもんめ』で語り手に取り憑いた「影」である。宮本作では語り手に正直な心の内を語るように促すが、藤田作では実際に姿を現し、彼女たちの過去の場面を再現する(記録映画における所謂「再現ドラマ」に当たる)。芳の場合は、大連での華やかだった思い出と引き揚げの際に収容所に逃げ込んできた重傷を負った日本兵の死の幇助をした悲惨な思い出の二人分の「分身」が登場する。「分身」が二重化するのだ。
4人の他に登場する5番目の女性についても語らねばならない。日本名・楓を名乗る朝鮮人女性・尹承恩(ユン・スウォン)。4人の老女の世話役のような立場で、日本語は片言ながら光子や瀧江の話の聞き役も務める。一方で、彼女自身も過酷な過去を背負っていた。兵隊の行く先々についてまわった、というから「慰安婦」だったのだろう。彼女を演じた美苗は、実際に「楓」のモデルと思しきおばあさんに取材旅行で会ったという。言葉は通じないながら、いつも上機嫌で、「私達が笑えば、一際大きな声で彼女が笑った」という(前掲プログラム)。
『とりあえずの死』は昨年11月にハチマルによって上演された。29年ぶりの上演である。上演に当たって、女優が手薄なハチマルは新劇、小劇場を問わず、実に多士済々の俳優を劇団外に求めた。芳に扮したのはかつて黒テントの中心を担い、現在は名取事務所等で多彩に活躍する新井純、瀧江は流山児★事務所の伊藤弘子、貞美は俳優座の早野ゆかり、光子はハチマルの上野裕子、そして楓が劇団文化座の小谷佳加という布陣。演出はハチマル演出が2度目となる流山児★事務所所属の小林七緒。これを観て驚いたのは、「記録演劇」のドキュメンタリー性が薄まり、ドラマ性が濃厚になっていたことだ。それは決して悪いことではない。初演から30年余りもたっているのだから生な演技をと言っても、少しずつ演技が過剰になる(老女たちのメイクが不自然なほど過剰であったように)。だいいち、最年長の新井にしてからが初演の村瀬幸子とは一回り以上の年齢の差があった。他の3人も推して知るべし、だ。もう、戦争経験者もいない。それでも満蒙開拓団の悲惨な引き 揚げの記憶は十分に伝わった。
小林の演出もよかった。本来は2幕の芝居を1幕にし、一気呵成に見せてしまう。老女4人の運命の酷薄が薄まったかもしれないが、大詰で歌われる「流浪の旅」など感傷に流れず、感動を新たにした。何よりも、戦後80年の昨年にこの戯曲が上演されたことに意義を感ずる。他に、満蒙開拓団や引き揚げを扱った芝居はなかった(わずかな例外は劇団匂組の『当番の娘』がある)。

|